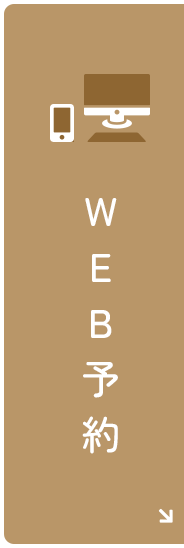マスク生活で影響を受けた子どもたちへのアプローチ
- 2025年10月6日
- 虫歯治療
こんにちは
たまご歯科クリニックです。
マスク生活の影響を受けた子どもたちへの口腔ケアアプローチについてお話しします。
1. 現状を把握することから始める
まずは子どもの口腔状態を正確に把握することが重要です。鏡を使って親子で一緒に歯や歯ぐきの色・形を観察し、歯垢や色の変化、歯ぐきの腫れなどがないか確認します。定期的に歯科医院で検診を受け、レントゲンや口腔内写真で虫歯や歯肉炎の進行度をチェックすることが、改善の第一歩です。
2. 口呼吸の改善
口呼吸は虫歯リスクだけでなく、歯並びや顔の成長にも影響します。改善には以下の方法が有効です。
鼻呼吸トレーニング:日中に口を閉じて鼻だけで呼吸する練習を行う
口閉じテープの活用:就寝時に専用テープで口を軽く閉じる(安全に配慮)
姿勢改善:猫背を直し、舌が自然と上あごにつく姿勢を保つ
鼻づまりがある場合は耳鼻科で原因を治療し、鼻呼吸しやすい環境を整えます。
3. 唾液の分泌促進
口腔乾燥が続くと細菌が繁殖しやすくなるため、唾液分泌を促す習慣を取り入れます。
こまめな水分補給(無糖の水・お茶)
キシリトール入りガムやタブレットを噛む
よく噛む食事(繊維質の野菜や固めの食材)
これらにより、唾液の自浄作用が働きやすくなります。
4. 間食習慣の見直し
虫歯菌は糖分をエサに酸を作り出します。ダラダラ食べを避け、間食は1日1〜2回に限定します。甘い飲み物やお菓子は食事と一緒に摂ると、歯が酸にさらされる時間を短縮できます。食後には必ず歯磨きやうがいを行い、糖分を口に残さないことが大切です。
5. 正しい歯磨きとフッ素活用
歯磨きは1日2回以上、特に就寝前は時間をかけて丁寧に行います。仕上げ磨きは小学生低学年まで、場合によっては中学年まで続けると効果的です。
フッ素入り歯磨き剤を使用(500〜1000ppm、年齢に応じて)
歯間ブラシやフロスで歯と歯の間も清掃
定期的なフッ素塗布(歯科医院や自治体のサービスを活用)
6. 専門家による継続的フォロー
歯科医師・歯科衛生士による定期的なメンテナンスは、家庭ケアの補完になります。特に進行した虫歯や口呼吸が続く場合、早期の治療や矯正による改善が必要なこともあります。
年2〜3回の定期検診
虫歯予防プログラム(シーラント、フッ素塗布)
口腔機能発達不全症への早期対応
7. 家族全体での取り組み
子どもだけでなく、家族全員で健康な生活習慣を共有することで継続しやすくなります。
家族で一緒に歯磨きタイム
甘い飲み物を常備しない
外出先でも水筒に無糖飲料を持参
親が手本を見せることで、子どもも自然と良い習慣を身につけます。
8. 心のケアも忘れずに
コロナ禍による生活変化は、子どもにストレスを与えることもあります。ストレスは食欲や間食の増加、口呼吸の癖につながることがあるため、安心できる環境づくりも大切です。スキンシップや会話の時間を増やし、生活リズムを整えることで、口腔だけでなく全身の健康も守れます。
まとめ
マスク生活や生活習慣の変化によって口呼吸や虫歯リスクが高まってしまった子どもたちも、早期の対策と継続的なケアで口腔環境は十分に改善可能です。家庭での予防習慣と専門家のサポートを組み合わせ、口の健康を守ることは、将来の全身の健康にもつながります。
【監修】 歯科医師 中野真伍
2014年3月
大阪歯科大学卒業
2015年4月
大阪歯科大学付属病院にて研修
2016年4月
大阪市内の歯科医院にて研修
2021年4月
医療法人正歯会たまご歯科クリニックにて院長として就任
現在に至る