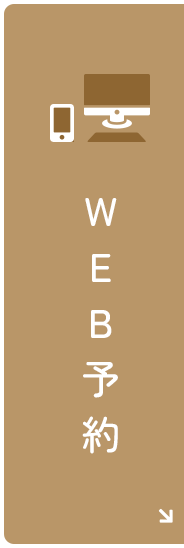コロナ渦でのマスク生活と子どもの虫歯リスク増加の関係性
- 2025年9月11日
- 虫歯治療
こんにちは。
本日はコロナ禍のマスク生活と子どもの虫歯リスク増加の関係性についてお話しさせていただきますね。
1. マスク生活で何が変わったのか
新型コロナウイルス感染症の流行により、日本では長期間のマスク着用が日常となりました。感染症予防には有効でしたが、その裏で子どもたちの口腔環境には大きな変化が起きています。近年、歯科医院からは「虫歯の子どもが増えた」という声も聞かれ、その原因の一部にマスク生活が関わっていると考えられています。
2. 口呼吸による口腔乾燥
マスクをしていると呼吸がしづらく、特に運動時や会話時に無意識に口で呼吸しやすくなります。口呼吸は口の中を乾燥させ、唾液の量を減らします。唾液は食べかすや細菌を洗い流し、虫歯菌の出す酸を中和する役割を持つため、減少すると虫歯菌が活動しやすくなります。長時間の口腔乾燥は、虫歯だけでなく歯肉炎や口臭の原因にもなります。
3. 水分摂取の減少
マスク着用中は、授業中や外出先でこまめに水を飲む機会が減ります。その結果、口の乾きが進行し、細菌の繁殖しやすい環境になります。特に糖分を含む飲み物を避け、無糖のお茶や水で口を潤す習慣が重要です。
4. 自宅時間増加による間食習慣
コロナ禍での休校や外出自粛により、自宅で過ごす時間が増えました。その間、子どもがお菓子や甘い飲み物を摂る回数が増え、「ダラダラ食べ」の習慣がついた家庭も多いでしょう。口の中が長時間酸性になると、歯の再石灰化が追いつかず、虫歯が進行しやすくなります。
5. 歯科受診機会の減少
感染への不安や、学校歯科検診の延期・中止によって、定期的な歯科受診が減りました。これにより、初期の虫歯や歯肉炎が見逃され、発見時には進行しているケースが増えています。早期発見の機会を逃すことは、治療の負担や費用の増加にもつながります。
6. 実際に見られる傾向
日本小児歯科学会や一部歯科医院からは「コロナ後に虫歯の進行が早い子が増えた」「口呼吸や口腔乾燥、歯肉炎が目立つ」という報告があります。特に口呼吸は、虫歯だけでなく、歯並びや顔の骨格発育にも悪影響を及ぼすため、長期化させない工夫が必要です。
7. 家庭でできる予防策
鼻呼吸を意識:日中・就寝時ともに口が開いていないか確認
こまめな水分補給:無糖の水やお茶で口の乾燥を防ぐ
間食の時間を決める:ダラダラ食べを避け、食後はうがいや歯磨きを行う
丁寧な歯磨き:1日2回以上、特に就寝前はフッ素入り歯磨き剤を活用
定期的な歯科検診:感染対策をしながらでも年2〜3回は受診する
8. まとめ
マスク生活は感染症予防に有効でしたが、子どもたちの口腔環境には思わぬ影響を与えました。口呼吸や口腔乾燥、生活リズムの変化による虫歯リスクは確かに存在します。保護者が生活習慣を見直し、口腔環境を整える工夫をすることで、マスク時代に生じたリスクを減らし、子どもたちの健やかな成長を守ることができます。
【監修】 歯科医師 中野真伍
2014年3月
大阪歯科大学卒業
2015年4月
大阪歯科大学付属病院にて研修
2016年4月
大阪市内の歯科医院にて研修
2021年4月
医療法人正歯会たまご歯科クリニックにて院長として就任
現在に至る